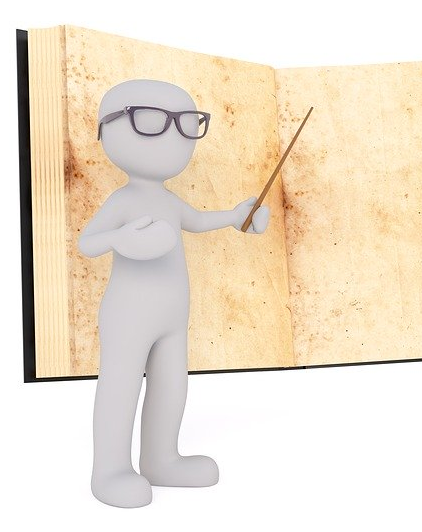ライン設計のエキスパートが生産性向上のためのノウハウを解説!
なぜ人気なの?3つのポイント
1. 知識と経験を兼ねそろえた講師による解説
2. 実用的なデータが豊富に記載されたテキスト
3. 具体的な投資効率の考え方が学べる
優れた生産ラインを構築するには、生産設備や生産ラインの自動化が不可欠ですが、決して一足飛びにできるものではありません。まず、工場・設備・作業の改善の考え方、進め方を知り、次に自社の自動化のレベルを把握し、そして投資効率を考えた設備設計を行う必要があります。本講座では設備設計の第一人者である講師が、生産ラインの自動化に必要な道筋を、基礎から丁寧に解説します。
課題を解決しよう!
よくあるニーズ
- 今後自動車業界ではどのような変革が起きるのか?明確なデータに基づいた情報が欲しい
到達目標 GOAL
- CASEに代表される次世代自動車に求められる技術進化の方向性の理解
- 現在、未来における自動車業界の問題と課題の理解
- 上記を踏まえた次世代自動車のロードマップの在り方
受講の対象者
- 自動車関連メーカーの研究開発職の方
- 自動車関連メーカーの設計職の方
- 自動車業界の今後の流れを掴みたい方
受講者の声
- 様々な情報や考えが錯綜しているが、明確な指針と理論に基づいた講義は大変参考になった
- 各国、各メーカーの動きや狙いを知ることができた。
- 業界動向、インフラ課題と政経との連動など期待通りの情報収集が行えた。
講師 藤村 俊夫先生の紹介
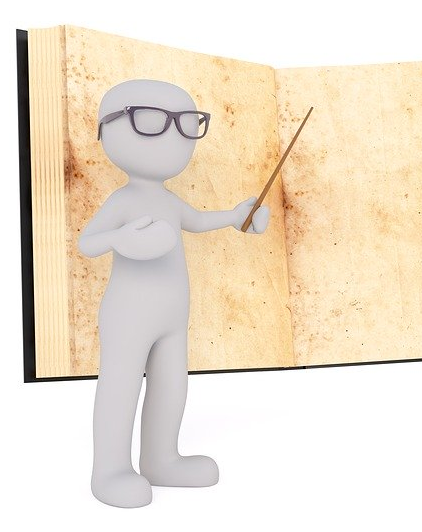 |
藤村 俊夫先生
経歴:1980年トヨタ自動車工業入社。入社以来30年間、本社技術部にてエンジンの設計開発に従事。専門はエンジンの機能部品設計(噴射システム、触媒システムなど)と制御技術、および各種性能改良。2004年に基幹職一級(部長職)となり、将来エンジンの技術シナリオ策定に従事。2011年より愛知工業大学に出向(2015年に転籍)機械学科教授を経て2017年に独立。現在は自動車関連技術のコンサルタントとして活躍している。
|
担当からコメント
ご専門はエンジンですが、国内外を問わず自動車業界全体の最新のデータ、流れを常に掴んでいる先生です。
会社員時代の経験も合わさり国内でも有数の自動車の専門家ですが、うらはらに非常にフランクな性格で親しみやすい先生のご講演はオススメです。
研修内容
| 1883年にカールベンツが世界初の3輪ガソリン車を開発、その後1900年代に入りヘンリーフォードが自動車の大量生産を開始し近代モビリティー産業を確立した。ここにきて、自動車産業はまさに130年に一度の大変革に迫られている.ユーザは自動車を保有することから利用する方向にシフトし、自動車メーカはモビリティーサービス(MasS:Mobility as a service)を提供する方向への転換が必要となってきた。
このような状況を踏まえ、本講座では今後の自動車産業とその技術について、大きく2つに分けて解説する。一つ目は今後自動車メーカが規制・顧客ニーズ双方の要求を満足するための技術開発はどうあるべきか、内燃機関をどういう形で残していくか、技術的観点から電動化(HV,PHV,EV,FCV)の優先順位はどうあるべきかについて解説し、2050年にむけたロードマップを提示する.二つ目はCASE(コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化)に関して、今後コネクティッドとシェアリングを普及させることの重要性と、一方で電動化と自動運転については今の進め方では非常に危うく、現状の重点課題と今後何を検討すべきか解説していく。
三つめは、まさに現在4輪車はユーザーが保有するから利用する、自動車メーカは製造・販売からサービスを提供する方向に変革すると言われる中、この交通形態の変化は急激で、スマートシティーを軸にいまや4輪車は交通手段の一部とみなされる社会に転換しようとしていることについて解説する。 |
<☆プログラム>
<習得知識>
・全産業を対象として、2030年までに2019年比でCO2の48%削減を実現するためには、電力のみならず燃料のグリーン化が必須であることが理解できる。
・自動車のCO2削減は、新車のみならず既販車を含めた保有車が対象となる。そのため、新車のCO2削減だけでは不十分であり、既販車のCO2削減が可能なdrop in fuel の市場導入が必要であることが理解できる。
・drop in fuelの量産化においては、再生可能発電の最大活用とヒートマネージメントによる効率最大化を考えると、送電線に連結しないオフグリッドプラントの必要性が理解できる。
・政治的思惑で、欧州委員会、欧州メーカが進めてきたEV偏重主義は、いずれ破綻することが理解できる。
・政府が進めるべきことは、EV推進を叫ぶことではなく、規制強化とdrop in fuel(炭化水素系のカーボンニュートラル燃料)開発の推進であり、カーメーカはxEVの開発と合わせ軽量化の推進が必須であることが理解できる。
・保有車を対象に、2030年までに2019年比でCO2の48%削減を実現するための道筋とシナリオ策定の手法が理解できる。
<プログラム>
第1章 気候危機の脅威 CO2低減は待ったなしの緊急課題!
1.気候危機の連鎖がいよいよ始まる -世界各国での未曽有の自然災害の多発-
2.地球温暖化とウイルス・細菌の蔓延は無縁ではない -シベリアでは炭疽菌が既に流出-
3.COP26における世界平均温度抑制目標の見直し(2.0℃➡1.5℃以下)の理由
4.IPCC6次レポートでの報告内容 -2030年CO248%削減のハードルは非常に高い-
5.COP26(英国グラスゴー)での成果 -各国リーダは未だ覚悟が足りない-
6.COP27 (エジプトシャルムエルシェイク)での成果 -2030年削減目標は未だ決まらず-
7.地球温暖化から地球沸騰へ -世界主要都市で連日40℃超え-
第2章 電力および燃料のCarbon Neutral化なくして2030年までにCO248%削減は不可能
1. 化石燃料は無限ではない。-迫りくるエネルギー危機回避にはCarbon Neutral燃料が必須-
2.各国の新車のCO2規制動向と保有車全体でのCO2削減効果(欧州と日本の例)
3. 運輸を含め、全ての産業におけるグリーン燃料転換戦略(エネルギーの種類と供給量)
4. 合成液体燃料(e-fuel)、合成ガス(合成メタン、NH3)などのカーボンニュートラル燃料の製造法
5. オフグリッドプラントとは? 何故オフグリッドプラントが必要か?-コスト、供給量、効率-
6.オフグリッドプラントの構成? -DAC、再生可能発電装置、共電解装置、FT反応装置、精製装置、熱マネージメントシステム-
7. 水素キャリア(メチルシクロヘキサン)製造の重要性と技術動向 -ようやく動き始めたENEOS-
第3章 各種技術課題への対応とxEV導入の優先順位
1.自動車の大分類(エンジン車とxEV)
2.ストロングハイブリッドシステムの分類
3.欧州メーカ初のシリーズパラレルハイブリッドシステム(ルノー e-Tech Hybrid)
4.ボディー軽量化(マルチマテリアル、高張力鋼板、Hotスタンプ材・・・・)
5.電気自動車の技術動向
6.電池技術の動向 -Liイオン電池の性能向上は限界➡全個体へ-
7.電池のエネルギー密度が低い現時点では超小型EVが現実的 大型のEVは負のスパイラル
8,主要4か国のLCA CO2はHEVがEVよりも少ない -EVはCO2が少ないという大義は幻想-
9.技術的な背景をベースに客観的に考察したxEV導入の優先順位
第4章 各国政府の電動化戦略と国連の示すCO2削減目標との整合性
1.各国政府の自動車の電動化表明とその裏にあるもの
2.中国、欧州連合(EU)、米国政府の電動化戦略の違い(ZEV化など) -EVに盲目的に突き進む欧州連合-
3.欧州委員会の「2035年エンジン車廃止規制提案」は愚策
4.ドイツ政府の反旗(e-fuelで走行するエンジン車を認めよ)は単なるエンジン車延命手段
5.EVに傾注してきた中国がHEV拡大に舵切り 中国は他国と比較し現実的なロードマップを描く -日本メーカに追い風、欧州メーカは逆風-
第5章 主要自動車メーカーの電動化戦略と動向
1.各国主要メーカーの4輪自動車の電動化戦略
2.各国主要メーカの電動化表明とその裏を読む -EV傾注に懐疑的になってきた欧州メーカ-
3.全方位戦略をとるトヨタとEV傾注戦略をとるVWの営業利益率比較
4.トヨタが2030年に向けたCO2削減シナリオを開示 -敵はCO2と言いながらあまりにも緩い目標-
5.各国主要5社の現状の電動化比率 -目標との乖離(かいり)が非常に大きい-
6.ストロングハイブリッド車の将来性 -いよいよ始まる中国、欧州でのHEVとBEVの戦い-
7.表向きは2030年にEV50~100%と言いつつ、裏ではPHEV機種拡大展開を進めるBMWとMB
第6章 世界の自動車の販売動向と電動車のシェア拡大動向
1.世界の自動車販売動向
2.世界の主要メーカーの販売台数推移
3.世界の販売台数の予測(2030~2050年)
4.補助金に大きく左右される中国、欧州のBEV、PHEV販売 -EV、PHEVの販売は補助金頼みであることが見えてきた-
5.欧州主要国のディーゼル車比率の急落とHEVの拡大 -補助金で売れるEVと補助金が無くても売れるHEV-
6.中国では補助金廃止とともにPHEVが徐々に拡大
7.中国のEVで上位を占めるLSEV(Low Speed EV)
8,中国「比亜迪(BYD)」米テスラ抑え「NEV販売世界一」 PHEVとEVの2つの駒を持つBYDに商機あり
第7章 保有車を対象に2030年までに2019年比でCO248%削減を達成するための道筋(シナリオ)
1. 世界の2030年、2050年に向けた内燃機関車、xEVの構成比率と保有車に占めるxEV比率
2.世界各国の2030年における、xEVの構成比率と年率のCO2削減目標
3. 2030年における世界全体の石油消費削減量とdrop in fuel(微細藻類バイオ、e-Fuel)の必要量見積もり
4.このシナリオでCO2削減目標は達成できる? 新たな課題は? -HEVコストが鍵を握る-
8章 まとめ
<講義概要>
2023年7月 国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、地球温暖化はいよいよ地球沸騰化に突入したと表明した。2023年7月は、産業革命以降でこれまでにない最高気温を記録したのである。自然災害は年々脅威を増し、各国で多くの人が犠牲となっているにもかかわらず、CO2削減対策は遅々として進んでいない。
自動車におけるCO2削減目標の対象は、新車と既販車となる。2030年までに2019年比でCO2を48%削減するためには、新車のCO2削減だけでは困難で、炭化水素系のカーボンニュートラル燃料であるdrop in fuel を、現在の石油消費の18%程度混合し、既販車のCOを削減することが必須となる。政治主導による補助金投入などでEVの販売を拡大してきたが、補助金を廃止した中国ではすでに陰りが出始めているうえ、欧州主要メーカのCEOなどもEV一辺倒は危ないとようやく気付き始めている。①CO2規制の強化(各国政府)と②xEVの効率改善(メーカ)、③drop in fuel の開発と市場投入のいずれが欠けてもCO2削減目標を達成することはできない。EV拡販政策は木を見て森を見ずの近視眼的政策だったのである。
本講座では、1~6章で自動車を取り巻く環境、drop in fuelの重要性および各種技術動向をまとめ、7章ではこれらをもとに、講師が作成したあるべきxEVのシナリオとCO2削減目標達成に向けての道筋を示す。
|