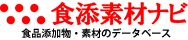※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
本講座では、微生物の進化と侵入経路の特定、簡易法の活用、規格基準の再構築など、実務に直結する微生物制御の最新知見を体系的に解説。製造委託先管理や家庭環境への対応まで踏み込んだ実践的な内容を提供します。HACCPの原点に立ち返り、リスクベースで迎撃態勢を構築する手法を学び、現場で活かせる衛生管理力を高めましょう。
微生物制御の基礎
|
| コード | tds20251223t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー(配信あり) |
| 日程/時間 | 2025年 12月 23日(火) 14:00~16:00 |
| 会場 | |
| 配信について | 録画配信です。(1/23までの配信) 開催後3営業日以内に配信開始します。 当日の受講が難しい場合は録画配信をご利用ください。 |
| ご案内事項 | 16時から18時まで講師・参加者を交えての交流会/相談会とさせていただきます。(会場受講者で希望者のみ) |
| 受講料 (申込プラン) |
会場受講: 16,500円 (消費税込) 録画配信受講: 16,500円 (消費税込) |
一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事 テックデザインパートナー講師 広田 鉄磨氏
ネスレのグローバル組織で海外勤務を 13 年経験、地方や国によって大きく食品安全の概念や座標が異なることを体感。帰国後は その経験をもとに 厚労省の HACCP 教育ツール開発グループメンバー、農⽔省主導の JFSM 創設準備委員会メンバー、JFS-A,B 監査員研修のテキスト編集。関⻄大学特任教授として食品安全を教えるかたわら 自ら創設した 一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズの代表理事となって現在に至る。 |
|
微生物の進化と存在の普遍性 |
|
|
日本においては、食品の衛生指標として「一般生菌数」および「大腸菌群」が採用されてきましたが、これにより工場での微生物対策がこれら指標に過度に依存する傾向が強まり、結果として本質的な衛生管理から逸脱する事例が多く見受けられます。本来、微生物制御体系は、第一義的に食中毒の原因となる病原微生物の管理を中心に据え、第二義的に品質劣化を引き起こす微生物への対応を補完的に構築すべきです。 |