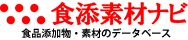※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
レトルト食品の開発は、加熱殺菌・包装・保存設計など多岐にわたる技術的配慮が求められます。本講座では、加熱による化学変化や微生物制御、包装材の選定、保存温度と賞味期限の関係など、製品設計における重要な留意点を体系的に解説します。講師は、厚労省HACCP教育ツール開発やJFS-A/B監査員研修などに携わる広田鉄磨氏。実務経験に基づいた具体的な視点から、レトルト食品の品質と安全性を両立させるための知見を提供します。製品開発・品質管理・技術選定に関わる方にとって、現場で即活用できる内容です。ぜひご参加ください。
レトルト食品開発の留意点
|
| コード | tds20251111t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 11月 11日(火) 12:30~17:00 |
| 会場 | |
| ご案内事項 | 熱殺菌工学を事前または事後に受講するとより理解が深まります。 |
| 受講料 (申込プラン) |
会場受講: 39,600円 (消費税込) |
一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事 テックデザインパートナー講師 広田 鉄磨氏
ネスレのグローバル組織で海外勤務を 13 年経験、地方や国によって大きく食品安全の概念や座標が異なることを体感。帰国後は その経験をもとに 厚労省の HACCP 教育ツール開発グループメンバー、農⽔省主導の JFSM 創設準備委員会メンバー、JFS-A,B 監査員研修のテキスト編集。関⻄大学特任教授として食品安全を教えるかたわら 自ら創設した 一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズの代表理事となって現在に至る。 |
|
1.内容物の化学変化 メイラード反応に代表される化学変化がレトルト過程で生じます。 2.化学変化の観点からレトルトに向かないもの メイラード反応が商品の風味にポジティブな効果をもたらすものはレトルトに向いているといってよいでしょう。 3.物理的な影響(変化) パウチの中に棘のような突起のあるものざらざらとした表面をもつものを入れ込むと(パウチの場合は熱で軟化した)最内層のプラスチックに傷をつけてしまいます。 4.物理的な影響(変化)の観点からレトルトに向かないもの 棘やざらざらとした外面を持つ具材はできるだけ避けた方が無難です。 5.微生物学的な変化 レトルト中は熱耐性の低い細菌から順に死滅し、最後は熱耐性の高い芽胞菌まで殺滅していくことになるのですがその芽胞菌を最低でも5D~6D(Log5~6ともいわれます)死滅させることが要件であることはあまり知られていません。 6.その後の賞味期限・保管温度で要求される殺菌条件 賞味期限が長いほど熱損傷を受けた芽胞菌が受けた傷を修復し終えて増殖してくる可能性が高まります。 7.レトルトの選択 PのT人窯、Hのオートクレーブ形式のレトルト窯、Rルーションの熱水浸漬型レトルト窯など名前を聞いてはっと気づかれるような方には大きな注意喚起をいたします。 8.結語 レトルトは古くからあるシステムであり、レトルト機器メーカーは過去の苦い経験をどんどん設計に生かし、コンピューターの組み入れによって可能となったフェイルセーフと相まって非常に信頼度が高まっています。 |
|
|
<受講対象> |