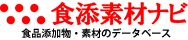※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
この講座の入門編ともいえる「賞味期限・消費期限の決定方法・延長方法・検証方法」の中では現在期限にかかわるどのような問題が起きているのか、問題を解決するにはどうやればいいのかという問題を起点とした一問題一ソリューションの模索という単純化された方式で学んでいただくことに力点を置きました。しかし問題を解決するには物理化学・生物学的なツールだけでは無理で予見・探知を必要とする課題、消費者の心理の中にソリューションがあるものについては限られた時間の中ではカバーできませんでした。もっと複雑な問題の解決にチャレンジなさる方々のための足場を提供することをこの講座の目標としています。上級編では「技術的な方法論」だけでなく、リスク評価・消費者心理・経営判断・社内合意形成といった多面的な視点を統合している点が特徴です。
賞味期限・消費期限の設定:上級編
|
| コード | tds20251203t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 12月 3日(水) 12:30~17:00 |
| 会場 | |
| ご案内事項 | 30分程度の簡単な予習動画がありますので、事前に視聴してください。(開催1週間前のリマインドメールに視聴方法を記載します。) 【注意事項】 会場が変更になりました。(紙媒体の記載から変更となっています。) |
| 受講料 (申込プラン) |
会場受講: 39,600円 (消費税込) |
一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事 テックデザインパートナー講師 広田 鉄磨氏
ネスレのグローバル組織で海外勤務を 13 年経験、地方や国によって大きく食品安全の概念や座標が異なることを体感。帰国後は その経験をもとに 厚労省の HACCP 教育ツール開発グループメンバー、農⽔省主導の JFSM 創設準備委員会メンバー、JFS-A,B 監査員研修のテキスト編集。関⻄大学特任教授として食品安全を教えるかたわら 自ら創設した 一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズの代表理事となって現在に至る。 |
|
1.期限を規定する項目 |
|
|
【上級編である要素】 |