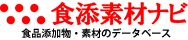<習得事項>
熱殺菌の基本が学べます。
この研修の中で明確になるのは今までどっかで習ってきたようなFo値計算できればすべてがうまくいくといった上っ面のソリューションではなく、F値計算式ですら菌の性格によって変化させないといけないこといったことを学びます。
熱の伝わり方によっては思ってもみなかった結末を招いてしまうこと、そしてさらに熱単独がオールマイティーなソリューションなのではなく包材の特性や(バイオフィルム生成に代表される)菌の独特な行動なども考慮しながら進めていくものだという理解にいざないます。
今まで習ったこともない内容が頻出してきて、この研修をもって熱殺菌の奥の深さを体感することができますよ。熱殺菌のファンがどんどん増えてくることを期待しています。
<講師の言葉>
「本講座に参加して修得できること」に書きました通り、皆さまにとっては今までに習ったことのない内容がどんどん出てきてびっくりなさることでしょう。そうなんです、熱殺菌という言葉が持つ古臭いイメージに縛られてしまって、そこに内包されている人類が過去に直面してきた苦難の歴史とそれを打ち破るための試行錯誤に気づかないまま、申し訳ないですが熱殺菌の上っ面だけを学習なさって来たというのが実際なのではないでしょうか?他の研修機関も批判に値します。10年一日100年一日のようにセピア色になり果てたFo値計算を繰り返し教え続けている。Fo値計算だけやっていればすべてうまくいくとでも言わんばかりに。そんな退屈な熱殺菌工学の概念をこの研修で打ち破ります。
熱殺菌は進化し続けています。熱殺菌工学の勃興はナポレオンがヨーロッパ大陸を蹂躙していた1804年ころの兵士用の携帯食糧の開発が始まりでした。それから220年以上の年月が経過していますが熱殺菌工学はヨーロッパ・アメリカ、そしてグローバルでは常に発展を続けています。食品製造にかかわる技術の中では初めてグローバルな連携が出来上がっているわけです。それなのに日本では第一次・第二次世界大戦を通じての孤立化を経て、軍需対応のための缶詰生産技術をもって発展が停止し、グローバルな切磋琢磨の波にもまれることなく今に至っているのです。
今回の研修の中ではすくなくとも第二次世界大戦の初頭から現在に至るまでの80年余の空白期間の中で世界で起きた変化を早回しで見ていただくことになります。
熱殺菌工学講座①︓⼊門編(微生物と殺菌値の計算)
熱殺菌工学講座②:初級編(殺菌手法のあれこれ)
など広田鉄磨がすでに上梓しているVOD(Video On Demand)をご覧になってから参加なさると、少なくとも自分の頭の中で疑問点が整理されてからの参加となるので有益です。しかし多くの方々は熱殺菌工学の最初の関門であるF値計算ですでに辟易となさっているので、事前のVOD受講は必須ではありません。VODはこの研修に参加してもっと勉強しようとなった際の二段目学習用に置いておかれても結構かと存じます。
ExcelでF値計算を実際にやってみるという作業がありますので、なじみの(Excel搭載済みの)PCを持参されたほうが学習の成果は上がります。しかしPCを持ってくるのは大変という方は研修中に講師が見せる手順を覚えて帰るだけでも十分かとは感じます。