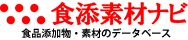※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
牛乳の殺菌方法を中心に、低温殺菌乳の特徴や利点・欠点を理解し、最適な利用方法を探ることを目的としています。殺菌の目的や歴史、技術的な区分と特徴、日本特有の製造・販売の特殊性、用途別の選択肢の提案など多岐にわたります。官能評価や加工特性の体験・相談も行われます。低温殺菌乳の品質維持と技術的課題についても具体的に掘り下げる予定です。
低温殺菌乳を知る:技術・品質・課題
|
| コード | tds20250701t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 7月 1日(火) 13:00~16:30 |
| 会場 | |
| ご案内事項 | 熱殺菌工学はこちら |
| 受講料 (申込プラン) |
会場受講: 33,000円 (消費税込) |
一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事 テックデザインパートナー講師 広田 鉄磨氏 ネスレのグローバル組織で海外勤務を 13 年経験、地方や国によって大きく食品安全の概念や座標が異なることを体感。帰国後は その経験をもとに 厚労省の HACCP 教育ツール開発グループメンバー、農⽔省主導の JFSM 創設準備委員会メンバー、JFS-A,B 監査員研修のテキスト編集。関⻄大学特任教授として食品安全を教えるかたわら 自ら創設した 一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズの代表理事となって現在に至る。 |
|
1.牛乳の殺菌の目的 牛乳には有害な菌がいるので、安全に飲むためには殺菌が必要です。 |
|
|
<講師の言葉> |