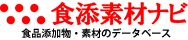※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
クレームを受けてから時間をかけること無く判断する事が必要な項目の対応方法を概説した後、食品の賞味期限を設定する上で特に重要となる客観的な指標項目(理化学試験、微生物試験、官能検査)それぞれのポイントを簡潔・明解に解説します。賞味期限を設定する上で起こりがちな疑問についても紹介し、対応方法を解説します。
賞味期限の根拠とすべき3つの試験
|
| コード | tds20250822n1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 8月 22日(金) 13:00~16:30 |
| 配信について | 対面からオンラインに変更いたしました(5月9日更新)。【見逃し配信】はありませんので、ご注意ください。リアルタイムでのご受講をお願いします |
| 資料(テキスト) | 電子データ(PDF) |
| 受講料 (申込プラン) |
早割価格: 23,760円 (消費税込) ※7/22までの申込み 通常価格: 26,400円 (消費税込) |
帯広畜産大学を卒業。これまで経験した品質管理業務は、養鶏場、食肉処理場、ハム・ソーセージ工場、餃子・シュウマイ工場、コンビニエンスストア向け総菜工場、たまご加工工場、大手スーパーマーケットなど多数。現在は食品安全教育研究所代表として、年間100箇所以上の食品工場の点検、品質教育を行っている。著書に『“食の安全”はどこまで信用できるのか』(株式会社アスキー・メディアワークス)、『ビジュアル図解 食品工場の品質管理』(同文舘出版)などがある。 |
|
Ⅰ.賞味期限設定の基礎知識と測定項目 |
|
|
<講演概要> |