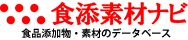※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
パン関連分野で開発に携わるためには、主原料である小麦粉の品質に関する知識と製パン理論の体系的な理解が欠かせません。入門者・初学者を対象に、主原料である小麦粉の知識と製パン工程の知識を、実務経験のある講師がくわしく解説します。
パン用小麦粉のハンドリング技術と製パン理論
~小麦粉の基礎、ブレンディング、既存の製パンシステム、オリジナル製法を産み出すコツ~ |
| コード | tds20251212t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 12月 12日(金) 13:30~15:30 |
| 資料(テキスト) | PDFデータのダウンロード |
| 受講料 (申込プラン) |
税込/テキスト付: 16,500円 (消費税込) |
|
|
神戸女子大学 家政学部管理栄養士課程/大学院家政学研究科 教授 甲斐 達男先生 学歴:九州大学農学部卒業、カンサス州立大学大学院修士課程卒業、AIB第127期Baking Science & Technologyコース終了職歴:鳥越製粉(株)(1980-2000)、西南女学院短期大学(2000-2002)、西南女学院大学保健福祉学部栄養学科(2002-2022)、家政学部管理栄養士課程/大学院家政学研究科(2022-)出向:理化学研究所特別委託研究員(1988-1990)、佐賀医科大学(現佐賀大学医学部)生化学講座研究生(1990-1992) 他所属学会:日本農芸化学会、日本生化学会、AACC International、日本生物工学会、日本食品科学工学会、日本食品衛生学会 等専門分野:穀物科学、食品科学、食品衛生学、生化学、分子遺伝学/博士(農学)、MS(穀物化学)現在の研究内容: 1.パネットーネパン種の乳酸菌と酵母の製パン特性解析、ゲノム解析、二次加工システム開発に関する研究 2.小麦粉を大豆粉で代替した糖質フリーのレシピ開発およびそれに適する大豆粉の特性解明に関する研究 3.自然酵母の分離同定と製パン性能の解析 |
|
1.パン用小麦粉の製造技術 |
|
|
<習得知識> |