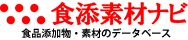※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
本講座では、食品の消費期限・賞味期限に関する法的定義から、設定根拠、保存試験や文書化のポイントまで、実務に必要な実践的な知見を幅広く解説します。
消費期限・賞味期限の設定根拠の正しい理解と実務への活用
~期限設定に必要なデータ・保存試験の設計・期限延長の技術とリスク~ |
| コード | tds20251010z1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 10月 10日(金) 13:00~17:00 |
| 配信について | 見逃し配信あり(視聴期間は10日程度) 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 |
| 資料(テキスト) | 電子ファイルをダウンロード |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格(PDFテキスト): 36,300円 (消費税込) 通常価格(PDFテキスト+カラー印刷製本テキスト): 39,600円 (消費税込) |
共創文化研究所 代表 高木 敏明 氏 東洋水産株式会社にて、食品の商品開発、品質保証や、HACCPシステム、ISO14001環境マネジメントシステムの構築・運用を担当。その後、全国チェーンコンビニエンスストアの事業協同組合にて商品開発・品質保証の支援に従事。2021年独立し、共創文化研究所を設立。現在は食品関連の中小企業を中心に、工場点検、衛生管理支援、HACCPシステム導入支援を実施している。 |
|
Ⅰ. 消費期限とは?賞味期限とは? |
|
|
<習得知識> |