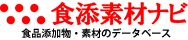※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
安全な食品を提供していく上で最もシビアに管理しなければならないのが微生物であり,食品に携わる技術者にとって微生物の知識と、殺菌や静菌技術の知識は必須である。微生物制御研究における著名な講師が殺菌効果の評価方法と加熱殺菌の理論を中心に各種制御技術のメリットやデメリットを解説する。今回は2日間かけて基礎と応用を講義する。
食品の殺菌・静菌技術と微生物の検出・計数・効果評価法
|
| コード | tds20251023t1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 10月 23日(木) ~24日(金) |
| 会場 | |
| ご案内事項 | <各講座ID(コード)と日程> 基礎編(tds2025102302):2025年10月23日 13:00~17:00 応用編(tds2025102401):2025年10月24日 10:30~16:30 <事前質問について> 講師へのご質問・ご相談は事前にご連絡いただいても構いません。講義の進行状況によっては十分な質疑応答の時間を取れないこともありますので、事前にご連絡いただけるとスムーズです。 ・ご質問・ご相談はこちらへ otaka★tech-d.jp(★を@に変えてメールしてください。) |
| 受講料 (申込プラン) |
両日受講: 49,500円 (消費税込) 基礎編のみ: 33,000円 (消費税込) 応用編のみ: 33,000円 (消費税込) |
|
|
大阪公立大学 研究推進機構 微生物制御研究センター 客員教授 土戸 哲明 先生 大阪大学工学部発酵工学科を卒業後、平成8年 関西大学工学部教授に就任。平成26年 退職(名誉教授)。平成28年から現職。現在は、有限会社トリビオックスラボラトリーズ取締役、日本損傷菌研究会代表、NPO法人カビ相談センター理事を兼務。また日本防菌防黴学会・日本食品工学会・日本生物工学会で各種役員を歴任。ライフワークとして食品殺菌・保存の他、医療関係や諸環境、文化財などの分野で微生物制御全般の研究に従事すると共に、微生物細胞の熱や薬剤によるストレスへの応答、損傷・修復機構、 損傷菌の動態解析・評価法開発などの基礎研究を推進。 |
|
1.はじめに―制御法・微生物・制御対象系の相互関係 |
|
|
|
大阪公立大学 研究推進機構 微生物制御研究センター 客員教授 土戸 哲明 先生 大阪大学工学部発酵工学科を卒業後、平成8年 関西大学工学部教授に就任。平成26年 退職(名誉教授)。平成28年から現職。現在は、有限会社トリビオックスラボラトリーズ取締役、日本損傷菌研究会代表、NPO法人カビ相談センター理事を兼務。また日本防菌防黴学会・日本食品工学会・日本生物工学会で各種役員を歴任。ライフワークとして食品殺菌・保存の他、医療関係や諸環境、文化財などの分野で微生物制御全般の研究に従事すると共に、微生物細胞の熱や薬剤によるストレスへの応答、損傷・修復機構、 損傷菌の動態解析・評価法開発などの基礎研究を推進。 |
|
9.併用効果の評価法 |
|
|
<企画背景と講演概要> |