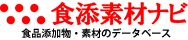※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
研究開発力の向上につながる知財スキル「特許調査」「特許の読み方・書き方」「クレーム解釈」「侵害回避」について、実務の現場で役に立つ実践的ノウハウを解説。
=生成AI活用を追加=
【期間限定】よろず先生の本当に役立つ知財講座
|
| コード | tdx20250701k1 |
|---|---|
| ジャンル | 知財 |
| 形式 | その他 |
| 配信について | 【視聴期間】申込完了翌々営業日~2025年8月31日 【申込〆切日】2025年8月1日 【配信内容】オンデマンド(2024/10~2025/5/4に開催したセミナーの動画となります) ※視聴期間中は、いつでも何度でも視聴することができます |
| 資料(テキスト) | PDFデータのダウンロード |
| ご案内事項 | ・視聴期間中は、メールで質問をお受けします。 ・1講座のみの受講はできません。 ・講義内容が重複するところがございます。 その点を踏まえた、お得な受講料となっております。 |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格(全5講座1アカウント): 99,000円 (消費税込) 複数割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※2アカウント以上でお申込みの場合 1受講割引価格(全5講座1アカウント): 79,200円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が1講座ある場合 2受講割引価格(全5講座1アカウント): 59,400円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が2講座ある場合 3受講割引価格(全5講座1アカウント) : 49,500円 (消費税込) ※5講座の中に受講した講座が3講座以上ある場合 再受講割引価格(全5講座1アカウント): 49,500円 (消費税込) ※技術者コースを過去に受講した場合 |
|
|
よろず知財戦略コンサルティング 代表、医学博士(元 大王製紙株式会社 知的財産部長) 萬 秀憲氏
花王(株)にて商品開発研究に従事(入浴剤バブ等を開発)、東京研究所室長、栃木研究所室長を務める。1999年 大王製紙(株)入社、 家庭紙開発部長、2005年よりH&PC事業部知的財産部長、執行役員、参与を歴任し2020年1月に退職。大王製紙(株)に入社当初は年間35件の特許出願数だったのを、様々な施策を行い、5年目には335件まで大幅に増やし、特許登録件数も年間300件以上となった活動を主導した実績がある。2020年4月より現職にて、延べ 十数社への知財戦略等のコンサルティング業務やセミナー講師など多岐に活躍。2021 年より知財 AI 活用研究会へ参加し、生成AIを含むAIの知財業務への活用を研究。 |
|
|
|
《プログラム》 |
|
|
《習得知識》 |
|
|
《プログラム》 |
|
|
《習得知識》 |
|
|
《プログラム》 |
|
|
《講義概要》 |
|
|
《プログラム》 |
|
|
《習得知識》 |
|
|
《プログラム》 |
|
|
《習得知識》 |