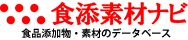※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
ベテラン機械エンジニアが自身の若手だったころを振り返り、「歯車設計で躓いたり、トラブルが発生したところ」や「事前にこういうところを勉強しておけばよかった」という内容で構成された歯車設計講座です。
~ベテラン技術者が若手設計者に伝えたい!~
設計する前に知っておきたかった歯車設計の基礎とポイント
|
| コード | tds20250724r1 |
|---|---|
| ジャンル | 機械 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 7月 24日(木) 10:00~17:00 |
| 会場 | |
| 受講料 (申込プラン) |
対面受講: 36,300円 (消費税込) |
伊藤精二技術士MDC事務所 技術士(機械部門) 伊藤 精二 氏 早稲田大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻課程修了。ソニー株式会社入社、生産技術本部・技術情報システム本部・エンタテインメントカンパニー/VTR走行系の機構設計開発・CAE解析/メカ3D-CAD/CAE設計技術開発・推進/二足歩行ロボットの企画開発・設計・マネジメントに従事。退社後、特許文献調査業務を経て、2013年よりエンジニア人材派遣会社にて機械工学・設計・製図研修講師、2019年より早稲田大学創造理工学部、2021年より日本大学理工学部で機械設計・製図カリキュラムの非常勤講師に従事。機械設計キャリア、機械工学・設計・製図教育講師を通じて、製品企画・概念設計・設計検討・詳細設計に至るまでの 『ものづくり』 全般に関わり、機械設計に必要な創造性育成を重視した設計技術力の向上・育成・教育に注力。 |
|
<目的・ゴール> |
|
|
<講義概要> |