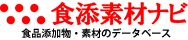※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
飲料の製造現場において必須の、充填前の殺菌技術、微生物の死滅曲線(TDT)とD値・Z値の関係、芽胞菌対策、各種薬剤の殺菌効果、アセプティック充填を含む充填技術、微生物事故防止対策を、講師の経験談や動画を交えわかりやすく解説します。
飲料製造における殺菌および充填技術の基礎と微生物事故防止
~ ミネラルウォーター・ソフトドリンク・アルコール飲料(Ready To Drink)~ |
| コード | tds20250805m1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | 対面セミナー |
| 日程/時間 | 2025年 8月 5日(火) 10:00~17:00 |
| 会場 | |
| 資料(テキスト) | カラー印刷製本テキストを当日配付 |
| ご案内事項 | <受講対象> 飲料工場の製造部門・品質保証部門の新入社員、若手スタッフ、将来の部門長やリーダーを目指している方などにおすすめ! |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 37,400円 (消費税込) |
㈱ティーベイインターナショナル 代表取締役 技術士(生物工学) 松田 晃一氏 1984年京都大学農学部食品工学科微生物生産学研究室卒業、キリンビール入社。全国6工場のビール&飲料工場で醸造、パッケージング、品質保証、工場建設を担当(計23年)。そのうち、パッケージング&工場建設が長く計18年従事。その中でいわゆる製造側(プロセス側)と設備設計施工側(エンジニアリング側)の双方の考え方、知識を学ぶ。専門は生物系だが、工場建設で機械と電気も経験。4年間のパッケージング研究所ではペットボトルの軽量化、バリア技術の開発に従事。キリンビバレッジ生産本部技術部長を最終ポジションに、キリン勤続30年で早期退職制度を選択し退職。自身の飲料ビジネスコンサルタント会社を2015年3月に設立、現在に至る。MBA、エネルギー管理士、公害防止管理者(大気・水質・騒音)、放射線管理者(第二種一般)、ビール検定2級、FSMS審査員補、英検準1級、通訳案内士(英語)、ドイツ語検定3級等の資格を持ち講演も多数。著書に日刊工業新聞社「おもしろサイエンス 飲料容器の科学」、NTS社「ボトリングテクノロジー(共著)、日本醸造協会誌「ワンウエイケグについて」119 (11), 577-587, 2024などがある。 |
|
Ⅰ.ミネラルウォーター・飲料・アルコール飲料市場のトレンド |
|
|
<本講座での習得事項> |