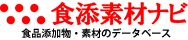※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
レポートや報告書といった文章の作成は、仕事の評価に関わるだけではなく場合によってはトラブルの原因になり得る重要な業務です。 伝えたい内容が相手に正確に伝わる文書を作成するためのテクニックを詳しく解説します。添削、評価する方にとっても有用な内容です。
分かる、伝わる、納得できる文書(報告書・レポート)の書き方
~結果を成果にする文書のコツ・ポイント~ |
| コード | tds20250804n1 |
|---|---|
| ジャンル | 汎用(品質,ものづくり) |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 8月 4日(月) 10:30~16:30 |
| 配信について | 【見逃し配信】はありませんので、ご注意ください。リアルタイムでのご受講をお願いします |
| 資料(テキスト) | 印刷物を郵送 |
| ご案内事項 | ◎本セミナーでは、コンサルタントや講師業の方(※)のご受講はご遠慮いただいております。 ※企業/大学等の所属有無を問わず実質的に社外に技術指導・講演をされている方(該当の有無をメールで確認させていただく場合がございます) ◎テキストをご自宅にお送りすることも可能です。お申し付けください。 |
| 受講料 (申込プラン) |
オンライン受講: 36,300円 (消費税込) ※本講座は早期申込み割引の対象外です |
ジャパン・リサーチ・ラボ 代表 博士(工学) 奥村 治樹氏 大手化学メーカー、電器メーカー、化学系ベンチャーでの研究開発とマネジメントに従事。現在はベンチャーから上場企業まで様々な業種の顧問や技術コンサルタントとして、研究開発、製造における課題解決から、戦略策定、人事研修などの人材育成などを行う(講師HP:http://analysis.ikaduchi.com)。また、学会等での招待講演や国プロにおけるキャリア形成プログラムの講師なども行っている。大阪産業大学 情報システム学科 非常勤講師、大阪市産業創造館 技術・経営相談員、市立教育研究所 運営委員、滋賀県 社会教育委員を兼務。知財管理技能士。 |
|
1.【イントロ:報告書、レポートとは】 |
|
|
<講演概要> |