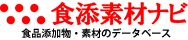※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
ダイエット・美容・老化・生活習慣病に関わる【糖質摂取と食後の血糖値】について研究データを紹介しながら分かりやすく解説します。
食後血糖値の測定ノウハウと″食べ方・食べ合わせ″による
~食後血糖値測定、食品の摂取試験方法と注意点、食後高血糖抑制作用、 グリセミック・インデックス、食後血中アルデヒド、血糖値と糖尿病~ |
| コード | tds20250425s1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 4月 25日(金) 9:30~15:30 |
| 配信について | 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 見逃し配信期間は4月28日(月)9:00~5月11日(金)24:00 です。 |
| 資料(テキスト) | 電子ファイルをダウンロード+印刷したテキストを郵送 |
| 受講料 (申込プラン) |
当日受講: 36,300円 (消費税込) 見逃し配信: 36,300円 (消費税込) |
同志社大学 生命医科学部 糖化ストレス研究センター 客員教授 八木 雅之先生 日本抗加齢医学会 評議員、糖化ストレス研究会 理事。日本ハーブ療法研究会 世話人。1990年~㈱ワイエムシィ研究部、1992年~アークレイ㈱研究開発・新規事業部門、2011年4月~同志社大学大学院生命医科学研究科糖化ストレス研究センター講師、2012年~同 准教授。2015年4月エイキット㈱生命医科学検査センターゼネラルマネージャー、糖化ストレス研究所所長。食品・化粧品等の糖化ストレス抑制作用評価を中心としたin vitro試験およびヒト臨床試験等の受託サービス事業を展開。2016年~2024年同志社大学生命医科学部糖化ストレス研究センター教授。2024年4月~現職。糖化ストレス抑制対策や抗糖化素材の機能性に関する研究、アンチエイジングや疾病予防としての抗糖化に関する普及啓発活動を展開している。 |
|
Ⅰ.血糖値とは |
|
|
<講演概要> |