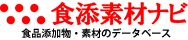※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
加工食品需要が増加し続けている水産練り製品に携わる技術者に! 世界で初めて冷凍すり身を産業化した創設者から4代に渡り冷凍すり身の製造・研究に携わる講師が、魚肉タンパク質の【冷凍】と【ゲル化】に関する基礎から最新の食感評価・テクスチャー制御手法まで解説します。
食感の改善に役立つ魚肉タンパク質の冷凍および
|
| コード | tds20250620h1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 6月 20日(金) 10:00~17:00 |
| 配信について | 見逃し配信もあります(視聴期間は10日程度) |
| 資料(テキスト) | 電子ファイルをダウンロード |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 36,300円 (消費税込) PDF+カラー製本テキスト : 39,600円 (消費税込) |
|
|
新潟食料農業大学 食料産業学部 講師 阿部 周司先生 2011年 東京海洋大学 大学院海洋科学技術研究科 博士後期課程を修了。2014年 東京工科大学 応用生物学部 応用生物学科 助教に着任。2021年より新潟食料農業大学 食料産業学部 食料産業学科 講師を務める。2008年 日本冷凍空調学会優秀講演賞 受賞、2020年 低温生物工学会奨励賞 受賞。冷凍すり身の産業化に世界で初めて成功した株式会社 阿部十良商店の創設者を曾祖父に持ち、4代にわたって冷凍すり身の製造・研究に携わる。現在は冷凍すり身のゲル化を主として、食品の食感(特に食品の冷凍による食感の変化)について研究を行っている。また、未利用水産資源の活用、青果物の冷凍にも取り組んでいる。 |
|
Ⅰ.魚肉タンパク質の扱い |
|
|
<習得事項> |