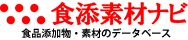※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
世界で最も生産され消費量が多い野菜である「トマト」について、カゴメで長い間、野菜研究に携わってきた講師が詳しく解説します。
トマトのおいしさ・調理方法と 機能性の研究成果(リコピンを中心に)
|
| コード | tds20250527s1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 5月 27日(火) 10:00~12:00 |
| 配信について | 見逃し配信あり(視聴期間は7日程度) 当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。 見逃し配信期間は5月29日(木)9:00~6月8日(日)24:00 です。 |
| 受講料 (申込プラン) |
当日受講: 22,000円 (消費税込) 見逃し配信: 22,000円 (消費税込) |
|
|
会津大学短期大学部 非常勤講師 元 カゴメ総合研究所 基礎研究部長、主席研究員 稲熊 隆博 紹介:1952年生まれ、同志社大学大学院工学研究科博士課程(前期)修了。農学博士 技術士(農業部門)。カゴメの総合研究所で基礎研究部長、主席研究員を経て現職。主な研究分野は、野菜と果物の機能性研究と食品加工。公益社団法人日本フードスペシャリスト協会名誉フードスペシャリスト。日本食品科学工学会学会賞、日本食品保蔵科学会技術賞を受賞、またシンポジウム等で講演。著書には、「世界を制覇した植物たち(学会出版センター)」、「野菜の色には理由がある(毎日新聞社)」などがある。 |
|
Ⅰ.世界を制覇した植物 トマト |
|
|
<講演概要> |