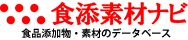※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
様々な食品で役割を果たす糖化品について、種類や構造から食品へのアプリケーションまでを網羅的に解説します。水溶性食物繊維や糖化用酵素といった新しい利用例、さらには最近の開発動向、昨今の糖質制限ブームを踏まえた今後の展望についても紹介します。
甘味料の基礎とアプリケーション
~甘味料の製造法・有用性・差別化ポイント・利用技術、最近の安全性情報と安全安心への配慮~ |
| コード | tds20250626n1 |
|---|---|
| ジャンル | 食品 |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2025年 6月 26日(木) 13:00~15:30 |
| 配信について | Live配信に加え【見逃し配信】も実施します。当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご視聴ください(配信期間は10日間程度) |
| 資料(テキスト) | 電子データ(PDF) |
| 受講料 (申込プラン) |
通常価格: 24,200円 (消費税込) |
小川技術士事務所 代表 技術士(生物工学部門) 博士(農学) 小川 浩一氏 大学院卒業後、食品製造会社(スタンダード上場企業)に入社。38年間で研究開発、営業、生産統括からコーポレートガバナンス部門までを経験。2023年9月、同社を退職後、技術士事務所を開業。食品産業の開発サポートや農産物加工販売の技術サポート、また食の最新話題をテーマとした講演活動を行う。(公財)静岡県産業振興財団 登録専門家。<所属学会等>日本技術士会(生物工学部会)、日本シクロデキストリン学会 |
|
Ⅰ.甘味料の基礎 |
|
|
<習得知識> |